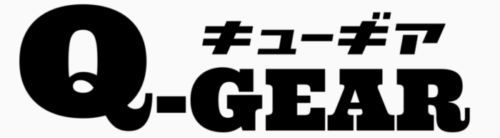夜兎族は宇宙3大戦闘民族だ。その強さ故に故郷の惑星は破壊され、残った民族は各惑星に移住を始めた。現在では絶滅危惧種とも呼ばれる貴重な種族である。
そして宇宙海賊春雨第七師団は夜兎族で構成されている。団長の鳳仙を筆頭に、強靭揃いだ。そんな第七師団は今、機械技師の人口が多くを占めるとある惑星にやってきた。この惑星は夕方から深夜にかけて必ず雨が降るという不思議な特徴がある。日中は曇りが多く、太陽が天敵である夜兎族には住みやすい街だった。鳳仙はある目的の為に惑星の中心部であるこの街にやってきた。
街を進むと朽ちたビルや煉瓦の家、瓦屋根に目が行く。それらはこの街に様々な文明が入り乱れていたことを示していた。
鳳仙に導かれるようにやってきた団員達だが、目的を知らされている人は1人もいなかった。彼の様子から何かを──あるいは誰かを──探していることは皆薄々察していたが、誰一人として彼に尋ねるようなことはしなかった。
それは当然この街を迷路のように彷徨う青年──阿伏兎も同じだった。彼が今いる場所は機械技師らが作ったであろうカラクリのガラクタが捨てられる場所、またはその実験場のようで、風変わりな金属の塊が山のように積み重なっている。建物と建物の間にガラクタの山があり──本来道である場所が進めず行き止まり、なんてことが多々見られた──それが迷路のように道を複雑化させていた。一度入ってしまったからには素直に引き返す気にもならず、阿伏兎はどうにかしてあるかもわからない出口を探し歩いていた。
こんなところを仲間にでも見られれば、今夜の酒の肴にされる事間違いなしだった。道を進んでも、道を引き返しても、そこを見られてしまえば終わりだった。どちらの選択をするか悩んだところである事に気がついた。
──自分がどの方向から来たのかわからなくなっていたのだ。
2択の問題だと思っていたことが実はもう既に手詰まりだった事に気付いて阿伏兎は絶句した。仲間に見つかればむしろ幸いなのだ。そのまま笑われながら船に戻ればいい話。しかしこのまま見つからず、迷路からも脱出出来なければ完全に置いていかれる。どんな手段を使おうともこの迷路から脱出しなければならない。もうどうにでもなれ!そう思いながら右手方向の道を進んだ。
「おじさん、そっちはなにもないよ?」
女の子の声だった。女の声ではなく、女の子の声。少し舌足らずな話し方だった。声を掛けられるまで少女の気配を感じ取れなかった阿伏兎はすぐさま振り向いた。
背後にいたのはやはり年端も行かぬ女の子。おかっぱ、おしゃれに言うならショートカットかボブヘア。髪に付いている金色の鈴と赤いリボンが特徴的な子だった。
「おじさんはまいごのネコちゃん?わたしはね、ウサギのおまわりさんだよ!」
「……」
えへん!と誇らしげに胸を張る女の子に、何も言えない青年の図はなんとも奇妙だった。阿伏兎は少女が何を言っているかさっぱりだった。
どうやら少女は、阿伏兎の状況を童謡に例えているようだ。童謡の中で、迷子になっているのは子猫、それを助けようとする犬の警察。しばらくしてから阿伏兎もその事に気づくのだが、今は全くわからなかった。
「……」
「あなたのおうちはどこ!?なまえは!?わたしは名前!ちゃんと字かけるの!えーっとね、こうやって……」
何も答えられない阿伏兎をよそに、童謡の通りに質問をしては、答える暇もなくノンストップで話は進む。そのままその辺にあった金属の棒で地面に自身の名前を書き始めた少女。ぎこちないバランスの悪い字で“名前”と書き記した。
「すごいでしょ!」
青年は何を話したらいいのか全くわからなかった。しかし少女の話に否定したい箇所はたくさんあった。
おじさんと言われるにはまだ早い歳である上に、ネコというよりは兎。この事を伝えたとしても話がややこしくなるだけだ、そう思った阿伏兎は簡潔に話した。
「出口はどこにあるんだ?」
「あっち!やっぱりおじさんはネコちゃんだ!」
「……ァ、俺もどっちかって言うと兎だがな」
「ウサギ!おなじ、名前とおなじだー!」
嬉しそうにその場でぴょんぴょん跳ねる姿はウサギだった。しかし阿伏兎が言うウサギは、夜兎を表す兎だ。少女がそれを知っているのかどうなのかは不明だった。
「きてー!」
そういうと少女は走り出した。道を案内してくれるようで、意外とすばしっこい少女を見失わないように急いだ。
この辺りに住んでいる子供なのか、阿伏兎とは違い一度も迷わずに出口にたどり着く事ができた。数分悩んだこの迷路も、答えが分かってしまえばあっという間だった。
「おじさんのおうちはどっち?はやくおうちかえらないと、みんながシンパイしちゃうよ」
夕日も沈みかけている時間帯。番傘も必要なくなるような時間帯で、まさに夜兎が本領を発揮できるそんな時間になりつつあった。
キョロキョロと周りを見渡しながら少女が言った。まだその話題か、少々驚きつつ返答に困っている所で渋い声が一声。
「オイ、阿伏兎の野郎が餓鬼の子守してやがるぞ」
団員の1人が細い路地から出てきた少女と阿伏兎を見ていたようで、腹を抱えながら大声で言いふらしている。近くにいた別の団員がその声を聞きつけ、数名が集まってきた。ギャハハと例に漏れず腹を抱える大男たちを見ても少女は泣かなかった。普通夜兎族のような屈強な大男数名に囲まれれば、いい大人でも冷や汗をかくものだが、人見知りをしないのかただの無知なのか、少女は全く動じずに口を開いた。
「おじさんのかぞく?おかーさんはいないの?」
少女の言葉でさらに大男達が盛り上がる。少女の純粋な疑問は大人にとっては面白いもので、腹を抱えるのも通り越して地面に転げて笑う大男達。
「阿伏兎の母ちゃんだってよ」
「家族って……ギャハハ!」
「オイ阿伏兎、きちんと答えてやれよ」
結局のところ迷う・戻る・道案内してもらう、どれを取ってもおなじ結果であった事を受け入れた阿伏兎が、頭を掻きながらこの場をどうやり過ごすか悩み始めた。
「あー、ひとまず道案内偉かったな」
「えへへー、これからはまいごになっちゃダメだからね?」
「……よく喋る餓鬼だな。お前さんもそろそろ家に帰んな。それこそ親が心配するだろう」
数分の間に夕日はほとんど姿が見えないくらいに沈んでいた。辺りには街灯がないようで、このまま夕日が沈めば暗闇で包まれてしまうだろう。
──そもそも、この少女はなぜこんな時間に、あんな迷路のような場所に1人でいたのだろうか。かくれんぼでもしていたのか?だがあの場には少女以外の気配はなかった。それなら何故──。
少女が首を横に振った。それはどういう意味なのか阿伏兎が尋ねる。
「きょうはジジがむかえにくるまで、おうちにかえってきちゃダメなの。ジジがいってた」
ジジ、恐らく彼女の祖父のことであろう。
──こんな時間でもか?
──うん。ぜったいにダメって。あめがふってきてもダメって!
周囲はほとんど暗闇に呑まれている。人が来る気配もない。それに雲行きも怪しくなってきた。もうじきこの惑星名物の夜雨が降るだろう。そんな場所に傘も持っていない幼い少女をこのまま置いていく訳にはいかない。そう阿伏兎は頭を悩ませるが、背後からの仲間の声で決断せざるを得なくなる。
「団長が探し物を見つけたようだぜ。その餓鬼置いてさっさと行くぞ」
仕方ない、団長の命令は絶対だ。俺も死にたくはないからなァ。そう言って阿伏兎は少女の元を去った。しかし少女は特に気にする様子もなく、ひたすら阿伏兎に手を振っている。飛び跳ねながら両手を左右にブンブンと振っては、バイバイと大声で叫ぶ。少女は余程阿伏兎の事を気に入ったようだ。
阿伏兎が鳳仙が待つ場所に着いたと同時に、彼の目の前を何かが勢い良く通り過ぎた。その何かがそのまま周囲の壁に叩きつけられた時、そこでようやく阿伏兎は何が飛んで行ったのか理解した。
「ゲホッ、鳳仙様……。お許しください……」
「例の子供を渡せ。そうでなければ貴様の命はないと言っておる」
その男の顔には見覚えがあった。鳳仙に首を絞められている老人は、同じ夜兎族であり、戦闘から一線を置いた技師だった。夜兎族は戦闘民族であるが故、腕や足を無くすものが多い。なので夜兎族は欠陥を補う技術が発展していた。阿伏兎がこの男を見かけたのも、彼が元第七師団の技師であるからだった。
男は地面に叩きつけられ、口からは血が流れる。夜兎族最強とも言われる鳳仙の一撃を受け瀕死のようだ。
例の子供、鳳仙の探し物が子供だった事に阿伏兎や団員は驚いた。子供1人を探す為にわざわざこの惑星の足を運んだのか。
そこまで考えて阿伏兎は思い出した。
──子供?
「知りませぬ、そのような子供……。我々は──」
先ほどまで一緒にいた名前という少女。鉄屑と瓦礫しかないこの惑星でどこからか現れた1人の少女。
──いや、ないない。
すぐさま思考を否定した。あんなちっぽけな餓鬼を探す為にわざわざ団長自らが赴くとは、これっぽっちも考えられな──。
「ジジ!!」
阿伏兎の後ろから少女が飛び出した。先程の子供──名前が倒れている男に向かって飛び出した。
「名前!何故帰ってきた!?今すぐ逃げ──」
男が叫び終わる前に鳳仙はその頭を踏みつぶした。なんとも形容できない、ナニカが潰れる音が一帯に響いた。
阿伏兎の耳を劈く少女の悲鳴。それも構わない鳳仙が口を歪めた。
「やはりここに隠しておったか」
必死に男の元へ向かおうとした少女の頭を、鳳仙の大きな手が包む。そのまま掴み上げられ、少女の足はバタバタと空を泳ぐ形になる。
予想通りの結果に鳳仙は喜びを隠しきれず、大声で笑い出した。
「ああ゛!!」
「忌々しい餓鬼め。この鳳仙に見つからぬよう必死に隠していたようだが、もう貴様を隠す者は何もない」
握った手に力を込めているのか、少女は苦しみながら足をバタつかせる。腕を蹴ようにも、その短い足では届かずただ痛みに耐えるしかなかった。
鳳仙の言う通りもう名前が隠れる場所はどこにもなかった。阿伏兎が周囲を見渡すと血の海で、あちこちに同族の死体があった。この街全体でこの少女を守っていたようで、鳳仙はそれを利用して名前を炙り出したのだ。
悲惨な光景だが、それが鳳仙のやり方だった。団員はいつものように、この状況に口を出さなかった。……1人を除いて。
「団長そこまでにしましょうや。あの春雨第七師団長が、こんな餓鬼を探すのに街人皆殺しって、そりゃあないでしょう」