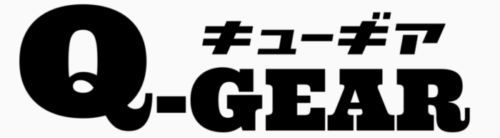天気の良い午後の真選組屯所は静かだった。だいたいの隊員は出払っているか昼食を口にしている時間帯であった。
中庭では洗い立ての白いシャツを、引き裂かんとばかりに左右に引っ張る名前の姿。先日の銀時との会話を思い出し、怒りがふつふつとこみ上げてくる。
「──生きて帰るぞ。その頃にゃ、お前の髪もヅラぐらい長くなってんじゃねえの?」
「──随分と髪が伸びたようだが、それ似合ってないからな?もしかして旦那の趣味?やめとけやめとけ。大体男の趣味に合わせて髪型変える女なんてなぁ……」
長い時間を経てようやく再会した2人であったのに、最悪な別れで終わってしまった。しかも、名前からすると一方的に罵られただけというから気分が悪かった。ぶちぶちと誰かのシャツが破れる音と、鬼の形相で歯を食いしばる名前の姿。顔は塀の方を向いているとはいえ、怒りのオーラが彼女を包む。背後にいる青年は彼女に話しかけるタイミングを失っていた。
「おう、元気か?」
「……土方さん。えぇ、元気ですよ」
青年は一つ咳払いをしてから、なんとも無いような口ぶりで声をかけた。
名前は突然後ろから声をかけられ我に帰る。そういえば今は仕事中であった。手に持っている破れかけのシャツを後ろに隠し、振り返った先には土方の姿。珍しく今は煙草をくわえていないようだ。
「どうかされましたか?」
「この前の礼をと思ってな」
土方が左手に持ったビニール袋を名前に突き出す。カサリと揺れたビニール袋は、半透明だが中身が何かわからなかった。首を傾げた彼女に、土方は昼食は済んだか確認を取る。
本日の名前のスケジュールは、掃除・洗濯がメインであり、ちょうどこの洗濯干しが終われば昼食の時間であった。それを伝えると、もう少しで終わる作業だったので、土方に少し待ってもらうことにした。急いで洗濯物を干すと、土方が座っている縁側に腰掛けた。
「マヨ団子の件だ」
「あぁ、それですか。いいんですよ、私が勝手に誘っただけですし」
「いや、あれ程までに美味いマヨ団子は初めてだ」
「それなら店主に言ってくださいな」
マヨ団子の味を思い出しているのか、空を見上げながら少しだけ頰を赤らめる土方。その横顔を見て、よほどマヨネーズが好きなんだなと謎の関心を抱いた名前。
「黙って受け取れ。ちょうど昼飯前なら尚更だ」
「なんですかこれは?」
「マヨにはマヨのお返しだ」
ビニール袋から取り出されたものはただひたすらに真っ白だった。使い捨てのプラスチック製の弁当箱に入った白い物体は、一見じゃそれが食べ物かは判断が付かない。
名前は頭の上に浮かんだままのハテナを消すことができなかった。この人は一体何の罰ゲームで私にこれを差し出して来たのか。それが正直な感想だった。
「土方スペシャル持ち帰りバージョンだ」
誇らしげに差し出すが、この食べ物らしき物の正体が何かがわからない。かろうじて上にかかっている物がマヨネーズと言うことは判断できる。が、問題はマヨネーズに埋もれている物がナニカ、だ。
通常の感性を持っている者ならば、この土方スペシャルとやらをちゃぶ台のごとくひっくり返してやるのが当然の反応である。が、これを受け取ったのはゲテモノ好きの名前だ。
一度はその存在を否定したものの、好奇心に勝てず言われた通りに受け取り、箸でマヨネーズの頂点を掬った。
マヨネーズ以外の存在を感じさせる感触はない。ならばこのマヨネーズは、一体どのくらい山盛りに盛られているのだろうか。更なる好奇心が名前を襲う。箸の先端はゆっくりとマヨネーズの沼に埋もれていく。
「おーいみんな、土方さんが人妻に手ェ出してるぞ。こりゃ大問題だァ!」
本当にどうでもいいマヨネーズへの探求を遮るように沖田の声が謎の緊張を緩めた。
名前を叫ばれた土方は、沖田の姿を確認すると腰にさしていた刀を抜いて、沖田へ斬りかかろうとする。
そんな事御構い無しに、名前は覚悟を決めて土方スペシャルを口にかきこんだ。
「マヨネーズだ」
味わって食べるが、どう足掻いても口の中にはマヨネーズの味しかしなかった。私は何を食べているんだ?これは哲学的な何かか?そう思いながら、土方スペシャルを食べ進めた。
確かにマヨネーズ以外の固い食感や、柔らかい何かが口の中に共存しているが、どれもマヨネーズ味。食べても食べてもマヨネーズ。もはやマヨネーズにマヨネーズをかけて、隠し味にマヨネーズを加えた一品なのでは?そんな意味がわからない事を考えているうちに、某猫とねずみのやり取りを終えた2人が名前が座っている中庭へ戻ってきた。
「このくだり、必要なのかなぁ?」
「シリアス展開になる前のギャグパートのつもりでさァ。で、近藤さんを探してるんだが、屋敷中探しても見つからねェ」
追いかけっこをしている際に、ついでに敷地内を探し回ったが見つからなかったようで、諦めた沖田が名前の隣に座り込む。名前が手に持っている土方スペシャルを見た瞬間に嫌そうな顔をした。
「あぁ、ゴリ……近藤さんを探していたんですね」
「どこにいるか知ってるんですかィ?」
「どこって、そこにいるじゃないですか、ホラ」
箸からスプーンに持ち替えた名前が土方スペシャルを口に含みながら、中庭にある木を指差した。つられて沖田と土方が木を見ると、そこには逆さ吊りにされた近藤の姿があった。顔面に貼ってある紙には「私はつまみ食いという禁忌を犯しました」と貼り付けてある。
「今日の晩ご飯はすごく豪華ですよ。ゴリラなんて捌いた事ないので緊張しますけど」
「さばくならもう裁いてますぜ。でもゴリラなんて食った事ねェから、毒味はまず土方さんに……」
「トシィイイイイ!!助けてくれ!!食われる!俺食われちゃうゥゥ!!!」
呆れて突っ込む事を忘れた土方。状況を整理するため、落ち着くために煙草に火をつける。
近藤が叫ぶ声が響くが、土方は聞こえないふりをした。名前が調理方を語る声、沖田がそれに反応する声。空を飛んでいる飛行機や、近所の騒音。全てに聞こえないフリをした。
ふぅっと吐き出された煙が風で揺れた。
「このくだり、いるか?」
「いらねーのか!?あ?せっかく人が帰りを待ってやったのによ!」
夕方、名前が仕事を終え帰宅しようと屯所を出たところ、門の前で銀時が仁王立ちで構えていた。一体なんだ、たまたま名前と一緒に屯所を出た山崎は思わずバトミントンのラケットを構えた。
銀時がカンタのごとくビニール袋を名前に突き出す。わけがわからない名前だったが、とりあえず山崎には仕事に戻ってもらうよう促した。何度も何度もこちらを振り返りながら、腑に落ちない顔をしたまま屯所を後にした山崎。
「いきなりどうしたの。あと何持ってるの?」
「宇治銀時丼」
昼間の土方スペシャルという名の、マヨネーズ一気ぐいで胃がもたれ気味の名前。袋から覗くいっぱいの小豆に、胃がSOSを出す。一体私は何をやらかせば1日に2度も罰ゲームを食らわなきゃいけないのか、と直近の自分の行為を見直す。
「悪いけど遠慮しておきます。もうすぐ夕食ですし」
「だから夕飯だって!差し入れ持ってきてやったの!」
これなら屯所でゴリラの丸焼きを食べた方がマシだ。そう思い、再び屯所の門をくぐろうとした名前の腕を銀時が掴んだ。
「ちょちょちょ、何戻ろうとしてんの?」
「おまわりさん、おまわりさん。おまわりさんというか土方さん来てください」
「よりにもよってマヨラーを呼ぶな!!なんだまだ反抗期やってんの?お前いくつ?」
グダグダウダウダ文句を言ってくる銀時に呆れた名前は、腕を振り払おうとするのをやめた。真っ向から相手してもダメだ、目の前の成人済み男性は、見た目は大人中身は子供のクソガキだと決めつけ、子供を相手にするときのように接する事にした。
「はいはい、わかったから腕離してね。もう暗いからお家に帰らないとママが心配してますよ〜」
「誰だよママって!あれか?お登勢のババアか?あのババアに母性なんて求めちゃいねーよ!」
「誰だか知らないけど、神楽ちゃんがお家で待ってるんでしょ?お腹すかせてそうだし、その差し入れとやらは神楽ちゃんにあげなさい。育ち盛りの女の子なのよ?」
「……今日神楽の奴はうちにいねぇよ。今頃新八の家で暗黒物質でも食わされて記憶飛んでんじゃねえの?」
「なに、喧嘩でもしたの?年端もいかない女の子と?そっちこそいくつよ?」
「っせーな、お前の想像してる喧嘩とは訳が違うんだよ」
夜兎族といういわゆる戦闘民族の娘である神楽との喧嘩は、それはもうバイオレンスであった。ただでさえ身体能力が人間よりも高い神楽のパンチ・キックを食らえば生身の人間はひとたまりもない。
「ま、どんな事情があろうと関係ない。今日は家に夕食の支度がしてあるの。夫も帰ってくるようだし、急がないといけないの」
「じゃあ家まで送る。お前の家どっち」
急に大人しくなった銀時の様子を見た名前は何かを感じ取った。さっきまでうるさかったクソガキが急に静かになる時は、だいたい何かを企んでいる時だ。
屯所の横に停めてあったスクーターから、ヘルメットを一つ名前に投げてよこした銀時は、自分もヘルメットを被り、スクーターのグリップに手をかけた。乗れと言うように、親指で自身の後ろを指す。
「あっち」
「あっちじゃわかんねーよ!」
「どっちと言われたらあっちそっちで返すしかないでしょ」
「屁理屈はいいんだよ。グダグダしやがって、早く次の展開行きたいの!文字の無駄!はい乗った!しっかり掴まってないと振り落とすからな!んで、お前の家どこ!?」
イライラしている銀時は名前を引っ張り、無理矢理スクーターの後部に座らせる。ヘルメットも被せ、ベルトを締め、自身の腰に手を回させた。
とりあえずスクーターを発進させ、名前に道を聞く。彼女の指示に従い、夜の道を走る。しかし、名前が素直に銀時の言うことを聞くことはなかった。
「そこをまっすぐ行って、次の角を左。その次の角も左、魚屋の角を左に──」
「って戻って来てんじゃねーか!!方向音痴かテメェはよ!」
「はい、誘拐犯逮捕。土方さーん、助けてください」
スクーターから降りて、真選組屯所に逃げ込もうとする名前を引き止める。
「お前どんだけ俺の事嫌いなの!?昨日の事か?昨日のせいでこんな嫌がらせしてくるの?あ、そうだ俺謝りに来たんだった。昨日は悪かった。だから面倒な奴に通報するのだけはやめろ。あいつらの事情聴取くそ長いから。サービス残業なんて可愛いネーミングしてるけど、あれ違法だからね?」
「わかったわかった。私だって早く次の展開に行きたいからもう黙って。そっちのノリに合わせようとすると無駄に文字数増えてパート分けるの面倒だから本当に静かにして。はい飛ばすよ、場面すっ飛ばしするからね。あとは地の文がなんとかしてくれる」
なんやかんやあって2人は苗字の家へとたどり着いたのだった。
というのはなしで、クソガキと屁理屈女の戦いは屁理屈女が折れてクソガキの勝利で終わった。素直に道を案内する名前と、二度目の苗字邸へのルートを絶対に忘れ無いように覚えながらスクーターを走らせる銀時。
スクーターのハンドルにかけられた宇治銀時丼が彼の運転に合わせて揺れた。