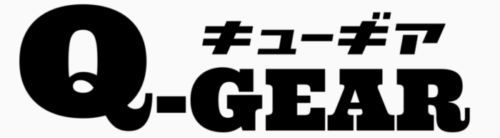「ダンチョー、臭いよ」
名前の目の前にいる血塗れの三つ編み男──宇宙海賊春雨第七師団団長である──神威はニコリと笑った。
任務だか、指令だかなんだか知らないが、わたし達は今はとある星にやってきている。数時間前に出て行ったダンチョーと阿伏兎は、行きと同じような、いつも通りの淡々とした雰囲気で帰ってきた。が、行きとは違い、酷い臭いがわたしの鼻腔を刺激する。
わたし達の生活は殺しが基本だ。好きで殺している者もいるけれど、多くの場合それが夜兎の本能だから仕方ないのだ。ダンチョーは好きで殺している方の種族だろうな。
「血生臭い、風呂、早く」
わたしの部屋から風呂場へは少し距離があった。部屋にはシャワーが設置されているが、シャワーごときでこの臭いが取れるわけがない。だから湯船にでも浸かって、さっさとその汚れと臭いを落として欲しい。わたしは風呂場方面を指差した。ついでに鼻も摘んで、あなた臭いですよアピールもしておく。
そもそも人の部屋に来るなら、綺麗にしてから来なさい。一応わたしは女であるので、その辺りは意外と気にしたりするのだ。
「飯」
わたしとダンチョーの会話は、側からみたら成立していないように見える。側からじゃなくても、どう考えても成立していない。わたしが風呂に入れと言えば、普通ならその返事はYESかNOだ。けれど、耳に返り血でも詰まったのか、ダンチョーは澄ました顔して「飯」の一言だった。YESでもNOでもない、飯という選択肢。会話のキャッチボールという言葉を知らないダンチョーに、ここで反論したところで無駄だろう。しかし一応反撃。
「食べてくればよかったじゃん」
「この星の料理は不味いんだ。だったら名前の飯の方がまだマシ」
「へいへい、そーですか。じゃあ作るから風呂入って。上がった頃には出来ているようにしておきますぅ」
見事返り討ちにされた。わたしが何を言おうが、ダンチョーはわたしに飯を作らせる気だ。飯を作るにしても、時間は必要だ。ダンチョーみたいに、大食いに食わせる飯ならなおさら時間が必要だった。
自分じゃ動かなそうなダンチョーを廊下へと押しやったところで、風呂場に向かおうとしている阿伏兎に遭遇。ついでにダンチョーを連れて行ってもらう事にすると、阿伏兎はやれやれと言った表情だった。32歳には見えない阿伏兎の老け顔は何が原因なのか。そんなの言われなくてもわかるだろう。
✳︎
ダンチョーって好きな料理あったっけ?そう思った時には既に調理は終了していた。なんでも食べるダンチョーだし、もう料理作っちゃったし、まあいいか。
厨房には炒飯の匂いが充満していた。めんどくさい案件を押し付けたお詫びに阿伏兎の分もある。この量を人間の胃袋に換算するなら30人前くらいか?人間の胃袋の小ささはよくわからないが、一般の夜兎族1人分ですらない、異常な量だけどダンチョーがいるならあっという間だろう。美味しいかどうかは別であるが、腹の足しにはなるまだマシなものだろうと信じている。
「いただきます」
わたしがそういう前からダンチョーはもぐもぐ、ムシャムシャと炒飯を胃袋に押し込んでいく。その姿をわたしと阿伏兎はやれやれと言った表情で見守る。その食欲を見ていると、こっちの食欲が失せる。ダンチョーを見ていると、自分もかなりの量を食べたような気になって、ちょっとしたダイエットになる。もうご馳走さまだ。
先に食べ終えた阿伏兎は、ごちそーさんと言ってわたしの頭を叩いてから自室へと消えて行った。食器くらい洗え。そう思ったが、一日中ダンチョーに付き添ったんだ。疲れているのだろう、休ませてあげよう。
視線をあげると大皿3皿目に突入しているダンチョー。この皿も洗うのか、そう思うとめんどくささが込み上げてきた。その時、炒飯を掻き込むダンチョーの前髪から、一滴の雫がポタリと垂れた。
「あ、ダンチョーちゃんと髪の毛拭かないと」
──ハゲるよ、という言葉を、喉ギリギリのところで引っ込める。
こんなに髪の毛長いのに、ちゃんと乾かしてないんかい。彼の父親には一度だけ会ったことがあるが、ハゲていた。ハゲの遺伝子は彼にも遺伝していそうだ。だからハゲという言葉は禁句にしていた。危ない危ない。
誤魔化すように自室へと一旦引っ込んで、ドライヤーとタオル、くしを引っ張り出してきた。地球で買ったナントカイオンが出る、髪に優しいと言われているドライヤー。タオルはこれまた地球で買った、高級タオルですごく吸水性が良い。
ダンチョーの長い髪をタオルで優しく包むと、手にじんわりと冷たさが伝わってくる。
「ダンチョーの髪の毛、さっきと違っていい匂いする」
じっくりと嗅いでるわけじゃない、ふんわりと優しい匂いがする。なんだろう、よく嗅いでいる匂い。そうだ、わたしが使っているシャンプーに似ている。これまた地球で買ったもので、香りが好きで購入したのだ。お気に入りなのだが、地球でしか売っていないためストックを買い込んでいる。だが、最近妙に減りが早い。仕方ないから、安くて容量が多い別の物に変えるか悩んでいる。
本当にその匂いによく似ている。似ているというより、同じだ。
「そりゃあ名前の使ったからね。そうだ、なくなったから新しいの補充しておいてよ」
「わたしの使ったんかい!!通りで減りが早いと思った!てか使い切ってるし!わたし今からお風呂入る予定だったんだけど、どうしてくれるの!?」
他にもツッコミたい事はいっぱいある。人の物を当然のように使うな!ましてや使い切るな!などなど、etc。くそ、こいつ平然と、涼しい顔して言っているんだろうな。ダンチョーの髪の毛を拭いているせいで、わたしには表情がわからない。いや、表情を見たところで、だ。
くそぉ、なんでわたしはこんな奴の髪を乾かしているんだ。自分で何をしているのかわかっているのか?わたしお気に入りのシャンプーで、お気に入りのドライヤーとタオル、またまたわたしのくしで髪のお手入れをしている。なんてお人好しなんだ、明日阿伏兎に慰めてもらおう。
「ダンチョーもこの匂い好きなんだね、意外」
ふと思い返すと、「いい匂いだね」からの「名前の使っているから」という会話から、ダンチョーとわたしはこのシャンプーの匂いが好きなのだろう。匂いを否定した様子はない。嫌いな匂いの人のシャンプーなんて、普通だったら使わない筈だ。
乾いてサラサラになった朱色を、今度は三つ編みにしていく。髪の束が交差するたびに香る匂いは、わたしとダンチョーお気に入り(?)の匂い。
「ごちそうさま」
かちゃりと蓮華が皿の上に置かれた。ダンチョーが食べ終わったのだろう。また会話のキャッチボールが出来ていない。が、ダンチョーがご馳走さまなんて、珍しい事もあるものだ。
「まって、もうすぐ終わるから。……はい、完成」
いたずらで結び目を可愛くリボン風にしてやろうと思ったが、バレた時が怖いからやめた。三つ編みは綺麗に完成。こう見えて手先は器用なわたしである。たまに云業の髪も三つ編みにしてあげている。
「今日はもう寝るよ。明日の朝食は、今の倍で頼むよ」
振り返らずダンチョーは言った。まじか、この倍ってアンタは吸引力の変わらないただ一つの掃除機か何かですか?
立ち上がったダンチョーからまたいい匂いが、ふわりとわたしの前で揺れる。わたしと同じ匂い。
あーあ、明日になったらこの匂い、また違う臭いに染まっちゃうんだろうな。
汚れた皿を手に流し台へと運んで、わたしはそんなことを考えていた。せっかくのいい匂いが、またあの生臭さに変わるとなると、心がモヤモヤした。ダンチョーも気に入っているとなると、また同じシャンプー買ってこないとな。