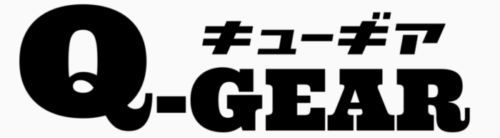「わたし、お兄さんのこと好きになっちゃった」
大好物である血糖値上昇アイテムのパフェを目の前にしたが、大きく開けた口は閉じることはなかった。パフェはひと口目が重要だとか、なんだかんだ言っていた銀時の口は開いたまま。反対に彼の目の前にいる女は、口を閉じ唇は綺麗な弧を描く。ただ笑みを浮かべるだけだった。
そもそもパフェを一つ頼んだのに、スプーンが2つ付いてきた時点でおかしいことに銀時は気付くべきだったのだ。
「えーっと、お宅誰だっけ……?ヨシコちゃん?ガキの頃近所に住んでたヨシコちゃん?」
「もう酷いなぁ、ついこの前会ったばかりだよね?もう忘れちゃったの?はい、アーン」
銀時の言葉に、女は子供のように頰を膨らませ残念そうに言った。パフェのてっぺんにある生クリームをスプーンですくうと、こぼした時のために左手を添えながら彼の口元へと運んだ。彼の口は相変わらず開いたままで、舌の上にスプーンについた生クリームが接触すると同時に我に帰った。異物を感知し、反射的に口を閉じると、待ち焦がれていた甘ったるさが口いっぱいに広がる。
「美味しい?」
銀時の口の中に生クリームを運んだ女は、今度は生クリームを自分の口へと運ぶ。
「やっぱり地球のご飯は美味しいね。そりゃあ団長が気に入る訳だよ」
へにゃりと笑う女。次々スプーンでパフェをすくい始める。いちごのソースと生クリームがかなり気に入った様子で、その美味しさを堪能している。
一方、銀時の方はというと、生クリームを特に味わうわけでもなく、機械的に飲み込んだ。彼の頭には「何か甘いものが口の中に入った」くらいの認識でしかなかった。頭が機能していないのだった。
この女はだれか。自分を知っている様子。この前会ったばかり。今わかっている情報を頭の中で整理しようとするが、上手く働かない。目をキョロキョロと動かし、唸る姿は壊れかけの機械にしか見えなかった。
「んー、どう説明したらわかりやすいかなぁ。誰だっけあの潔癖症男。えっとそうじゃない、クスリ…?うーん」
女の方も頭の中を整理するのでいっぱいで、同じく唸り始めた。しばらく唸っていたが、最適な言葉を思いついたようで、にっこり笑顔で銀時に告げた。
「春雨!」
「……!」
その瞬間、銀時の顔が変わる。警戒を表現するように目が鋭くなり、同時に思い出した。
「お前、ハム子ん時の……!」
「怪我はもう大丈夫なの?夜兎じゃないのに、治るの早いね」
2人の温度差がますます広がった。
銀時の記憶にも新しい、宇宙海賊春雨。先日仲間を助けに行った際に知ったその存在。危険信号が彼の頭の中に伝わり、警鐘を鳴らし始めた。警戒、殺気のオーラを放つ彼とは裏腹に、女は彼の左肩を右手人差し指でつん、と突いた。
「すごいすごい。下っ端とは言え、春雨の一部を潰しちゃったんだし、本当にすごいよお兄さん。そ・れ・に!春雨に木刀一本で立ち向かう奴初めて見た。これがサムライって奴?」
流暢に喋りながら、次に女はスプーンでパフェのイチゴを突っついた。
「てめぇ、何しに来た!」
「あれれ?何ってお兄さんに会いに来たんだよ?言ったじゃん、わたしお兄さんのこと好きになっちゃったって」
もう一度アーンと、すくったイチゴを銀時の口元へ運んだ。
相変わらずの殺気立った視線は、目の前の呑気な女に刺さる。これには流石の能天気な女にも伝わったようで、スプーンはUターンをして女の口元へ。
「ん。今わたしは任務じゃないよ。仕事終わりのプライベートでここに来てるの」
「プライベートも何も春雨って打ち明けた時点でお宅と仲良くする気はないってんだ。地球の次は俺のパフェを侵略しに来たってか?ふざけんじゃねえ」
「そうじゃないよ、わたしはお兄さんと一緒にパフェ食べに来ただけだよ」
「逆ナンって奴か?おいおい、とうとう俺もオヤジ狩りの対象に仲間入りって訳か。勘弁してくれ」
「違うって!わたしは会いに来たの!あなたに!もう、何時間も探したんだからね?」
最初の数分いがみ合うように会話していた2人だが、会話以外に注目すると、お互いスプーンでパフェを頬張っている。徐々に空になる容器に、白熱する2人の言い合い。
最後の一つになったスライスいちごを女がすくい取る。
「オイィィィ!!!それ俺のいちごォォォ!!」
「ご馳走さま!」
最後のいちごは女の胃袋へ。銀時は頭を抱えていちごへの思いを馳せる。
と、散々仲良くパフェを突いたところで、本来のシリアスシーンへと戻る。
「テメー、いい度胸じゃねーか!銀さんのいちごを食い散らかしやがって」
「名前」
「……は?」
「わたしの名前。お兄さんの名前は銀さんって言うのね。うん、覚えた」
数回銀さんと復唱すると、女は満足げに笑った。その無邪気な笑みを見ていると、彼女が凶悪な宇宙海賊の一員という事を忘れてしまいそうになる。
銀時も一瞬不意を突かれたように固まって動けなくなった。その隙を見逃さず、名前は窓ガラスを割り、外へと飛び出した。
「おにい……銀さん、近いうちにまた会うかもね。ううん、わたしが会いたいからまた会いに行くね。その時まで死んじゃダメだよ?」
「ちょ、待て!」
「ばいばい」
銀時が手を伸ばした時には名前の姿は風景の一部のように小さく、もう追いつけないような場所にあった。当然、届く事なく空を切った彼の腕は、力なくぶらりと元の位置へと戻る。数秒の間遠くを眺めていた彼だが、窓ガラスの音を聞きつけてやってきた店員の声で意識を戻した。
適当言って店員を追い払うと、再び席に着いた。突然やってきて、パフェだけ頬張って帰っていった女。数日前に会ったばかりの、自分のことを名前と言った女。数日前には、銀時らを助けるような素振りを見せ、今日は一緒にパフェを突くという奇行。その一連を思い出し、実は幻だったのではないかと疑い始める。しかし、ふと彼女が座っていた席を見ると、机の上にはスプーンと袋が置かれていた。
「……出口そこじゃねーよ、ったく」
袋の中には金と小さなメモ。練習したであろう丸文字で“パフェ代。またデートしようね。名前”と書かれている。それを見て銀時は大きなため息。そして、二度と会いたくないと思った銀時であった。
だが奇しくも、彼女の通りまた再び2人が出会う日がやってくるのであった。彼女の宣言通りに。