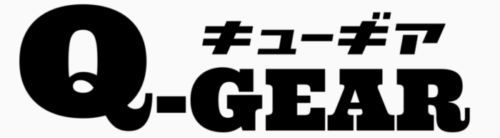キュッと名前は自分の髪をまとめているリボンをきつく締め直した。同時に髪飾りの鈴が柔らかく鳴いた。
「それで、この子は交渉材料でしたっけ〜?」
今から名前らはこの吉原桃源郷を作り上げ、太陽の光が差し込まない、自分だけの王国を作り上げた王の元へと向かう。それが何を意味するのか、名前はわかり始めていた。段々と近付いてくる自分と同じ気配。なるべく嫌なことを考えたくない彼女は、相変わらず云業の脇に抱えられている少年を見ながら言う。
彼女の前を歩く神威は楽しそうに答える。
「そ、エロジジイが隠している宝箱を開ける鍵だ」
「ふーん、鍵か。まだこんなに小さいのにね」
ぽんぽんと少年の頭を撫でる名前。少年は彼女に抵抗するように頭を数度振ったあと、睨みつけるように彼女を見た。
しかし少年はすぐに目を丸くした。意外にも名前の表情は悲しい顔をしていた。声色から彼女は神威と同じように嬉しそうな表情を浮かべていると少年は思い込んでいた。だから名前の表情は彼にとって意外だったのだ。さらに彼女の瞳はまるで自分ではなく別の誰かを思うような、そんな彼女の視線に少年は言葉を失った。
「そう?名前と同じくらいの年齢だと思うけど」
茶化すように神威が言ったが、言われた名前は何も返さなかった。代わりに少年の頭を撫でていた手をそっと離した。
少年にはわからないことが2つあった。一つはなぜ名前が悲しそうな顔をしているのか。もう一つは今神威が言った言葉だ。
少年と名前が同じくらいの年齢であるはずがない。少年の背丈と名前のそれは釣り合わない。頭2つ分の差は少なからずある。では何故神威はあんな事を言ったのか。名前の知能レベルを少年のものと同等と見たとも取れる。たしかに彼女は江戸を前にして即興の踊りを披露するレベルの知能指数であるが、神威が言いたかったのはそれだけではなかった。
神威の言葉には足りていない言葉があり、それを付け加えるとしたらこうだ。
「“あの時の”名前と同じくらいの年齢だと思うけど」
名前にはその足りない言葉が聞こえてしまった。だから黙ってしまったのだ。
実際に彼女自身も神威に指摘される以前に、少年に対して薄々既視感を抱いていたのだ。過去の自分に少しだけ似ている、交渉材料となってしまった可哀想な少年。哀れみと自嘲を含んだその表情が少年にも伝わったようで、彼からは名前の表情は悲しげなものに見えたようだ。
神威の言葉に微妙な空気が流れ込んできたので阿伏兎も云業も黙ってしまった。2人して「言ってはいけない冗談もある」と一言でも言いたかったが、それを言ってしまえばますます名前の機嫌が悪くなりそうなので黙った。だがこの気不味い雰囲気を破るには、王が待つ部屋にたどり着くか、誰かが別の話題を振るかの二択だ。阿伏兎が後者の選択肢を選ぼうと、咳払いをして喧嘩寸前の2人を仲裁しようとした。
「そーかもね」
しかし意外にも答えは二択ではなく、新たな一択だった。名前の方から口を開いた上に、喧嘩に発展せずそのまま言葉を受け流したのだ。
それを見た阿伏兎と云業は驚愕した。だが神威の方は相変わらず挑発を続けた。
「あり?怒った?」
「怒ってないよーだ!」
口をとんがらせながら名前は腕を頭の後ろで組んだ。神威のことなんて相手にしてないという態度を示している。しかし神威はそれを気にするつもりもなく、嘘くさい笑みを顔に貼り付けたままたどり着いた襖の前に立つ。
「名前、これ持ってて」
神威は名前に向かって羽織っていたマントや傘などなどを投げつける。それを一応受け取った名前はムスッとした顔で俯いた。反対に神威は清々しい笑顔で通された部屋を進む。
「さぁ師弟感動の再会だ」
当然のように師弟感動の再会、なんて表現は使われる事がなかった。
「うるさいなー!!」
がしゃんだか、どたんだか、様々な音が名前の鼓膜を振動させる。その前には女性の叫び声。接待の邪魔とされ、別室で待機していた彼女が、重い腰を上げて襖を開いた。
それと同時に、捕まえていたはずの少年とぶつかった。ぶつかった衝撃で少年は倒れこむが、腕を拘束されているため上手く動けない。
「いてて、大丈夫?」
少年の方はぶつかった相手が敵だと分かると目を見開いた。彼からすれば名前は先ほどまで自分を捉えていた者だ。脱走しようとした自分を見て、ひっ捕らえようとしているのだと思い込んでいる。自分に向けられた手に怯えた少年はギュッと固く目を瞑った。
しかしいつまでもやってこない衝撃に、少年は恐る恐る瞼を開く。衝撃どころか、先ほどまで感じていた圧迫感から解放された事に気付く。
「さ、この混乱?騒動?に合わせて逃げちゃいな」
「い、いいのかよ!こんな事して!」
解かれて床に落ちる紐に少年は驚いた。彼女が自分を逃がそうとしている……?何故なのか、彼には分からなかった。
「大丈夫、きっとダンチョーも元から君を素直に差し出すつもりはなかったと思うよー」
「そんな事…!」
「神威もワケアリみたいだし。……それとも、逃げたくないの?」
「……っ!」
逃げたくない、そんな訳なかった。少年は今すぐにでも母親に会いたくてたまらなかった。ずっと下から眺めることしか出来なかった母親に会えるものなら今すぐ会いたい。
そんな少年の顔を見た名前はニッと笑うと、彼の服に着いた埃を手で払った。着崩れも直してやると、早く行けと彼の背中を押した。
「さ、早くお母さん探しに行ってね。いいなぁ、私もお母さんに会いたい」
神威の交渉を別室で盗み聞きしてたおかげで、名前はこの少年の事情は少し把握しているようだ。
「なんでこんな、おかしいよお前!」
「ほらほら行った行った。会えるうちに会っておかないと、親は先に死ぬもんだからね」
少年の言葉なんか無視して名前は少年を廊下に押し出した。戸惑いながらも少年はようやく走り出す。それを彼女は笑顔で手を振りながら見送った。しばらく走ったところで少年が振り返ると、未だに手を降っている彼女の姿が見える。
少年には彼女が逃がしてくれた事が信じられなかった。逃がしたと思わせて追いかけっ子が始まるんじゃないか。母と一緒に始末するつもりで泳がせているのではないか。そんな不安が数々と頭を過ぎる。それでも少年の足は止まらない。愛する母の元へと急いだ。
廊下の角を曲がり、少年の姿が見えなくなったことを確認した名前は上司が起こしたであろうイザコザを確認しに部屋へと入った。
「で、何があったの?」
名前の視界には、睨み合う神威と夜王──鳳仙。瓦屋根に埋まる云業の姿。神威が発端なのは名前も粗方予想は付いていたが、まさか云業が屋根に顔だけ出して埋まっているなんて思ってもいなかった。云業は屋根から脱出すると、阿伏兎と名前の元へと合流した。
「あぁなるともう誰にも止められるねェよ……。余計な事起こしやがって、後始末させられる部下の気持ちになってみろ」
「止めちゃうの?」
「あったりまえだ、バカ娘」
そう言って阿伏兎と云業は喧嘩の横槍に入る。名前は「やめときゃ良いのに〜」と呟いて窓枠に腰掛けた。目下で上司の神威とやり合うのは自分の父親だと言うのに、名前には何の感情も湧かなかった。
師弟感動の再会があり得ない事も、親子感動の再会があり得ない事も当然だった。彼ら彼女らにそんなものは必要なかった。だから名前も一度も父親に焦点を合わせることなく目を逸らしたのだ。あの音が聞こえるまでは。
「なんだ、まだ怒ってる?名前も意外とねちっこいなぁ」
名前は屋根瓦でしゃがみこみ俯いていた。
──彼女が乱闘から目を逸らした直後、誰かが倒れる音で視線を戻された。仲裁に入ったはずの云業が倒れていた。側には血で染まった自らの手を舐める神威の姿。それを見た名前は声を上げた。仲間であり自分のお世話係だった云業がびくともしない。心臓を一撃で貫かれており瀕死だった。
「何も仲間同士の殺し合いに巻き込まれることなかったじゃん。ばか。云業がいなくなったら誰がわたしの髪結ぶの?」
名前はぼやく。そして彼の遺体にポケットから取り出した小枝から桜を一輪手向ける。
「ごめんね、これしかあげられないんだ」
まさかこんな所で云業が居なくなるとは思っていなかった彼女は、顔を上げると同時に彼を殺した神威に怒りの視線を向けた。
窓枠に腰掛けた神威は名前の視線を弾くように見下すような目で見た。彼女も負けじと威嚇しながら2人がいる部屋に戻った。
「俺だって腕一本持っていかれたんだ。心配くれェしてくれたっていいじゃないの」
「ふーんだ!団長とも阿伏兎ともしばらく口聞かないから」
「ありゃ、ドンマイ阿伏兎」
ケラケラ笑う神威を横目に阿伏兎は自分の腕の手当てを始めた。てっきり名前が手当てしてくれると思っていた彼は少し寂しそうにしている。しかしすぐにも上司の尻拭いが残っている事を思い出して作業に急いだ。その目の前を名前がドスドスとわざと足音を立てて通り過ぎた。
「名前どこ行くの?帰ろうよ」
「散歩!」
「あり?口聞かないんじゃなかったっけ?」
「これは独り言!!」
ぷんぷん怒りながら名前が襖を勢いよく閉めた。ドン!と音を立てた襖を見て阿伏兎がため息混じりにつぶやいた。
「これが反抗期ってヤツか。感動の親子再会だってのに、面倒なタイミングで来ちまったモンだ」
──結局一度たりとも名前と鳳仙の視線は交わることはなかった。云業のことで駆けつけた名前を見た鳳仙は、彼女の声を聞きはしたもののすぐさま「興が醒めた」と言って去ってしまったのだ。
阿伏兎は2人が少しくらい何か会話をするかもしれないとハラハラしたものだが、ありがたいことにお互いがお互いに不干渉で終わった。
「よかったじゃん阿伏兎。名前が本当の父親の元に帰る、なんて言い出さなくて」
「ほとんど全部お前さんのおかげだがな!」
ほっと一安心している阿伏兎の姿を楽しそうに見守る神威の前で阿伏兎が立ち上がった。怪我の手当が終わったようで、背後で帰ろうと急かす神威と共にマントをはらう。阿伏兎の仕事は彼の尻拭いだけではない。
「帰れ帰れ。こっちは誰かさんの尻拭いだけじゃなく、どうせ迷子になる運命の兎でも拾いに行かなきゃならないんだ」
「うちの船はゴミ捨て場じゃないんだろ?だったら迷子の兎なんて捨てていけばいいさ。ちょうどいい拾い手もここにいた様だし」
数時間前に自分の妹と共に居た銀髪のサムライの姿を思い出した神威は、いたずらを思いついた悪ガキのように口角を釣り上げて笑った。名前が好意を持ったというサムライとやらは彼であろうと神威は確信していた。だがあのサムライには強さを感じなかった。妹と一緒にいたと言うこともあり、その辺にいる弱い人間と同等と見做した。どうせなら仕事も碌にしない兎をここでクビにして、ついでにそのサムライにでも身柄を引き渡すのが名案だと彼は言った。
神威の「ここにいた」という発言に阿伏兎は一度足を止めた。同時に、最近名前の口から頻発し始めた“サムライ”という言葉が浮上して阿伏兎は冷や汗をかく。彼自身薄々勘付いていたものの、やはりあの銀髪の木刀を持った男が名前の想い人だとほぼ決定してしまった。名前は散歩と言ったが、彼女はあのサムライがこんな場所にいるというのを察知しているのかもしれない。彼女が持つ謎センサーが反応しているので散歩がてら探しに行ったのだろう。しかし彼女がお目当てを見つけたとして、そこにあるのはサムライの死骸だろう。そんなものを彼女に見せる前に彼女を回収しなければならない。
嫌な思考が頭をよぎり冷や汗が止まらないまま阿伏兎は振り返った。だが、思考を切り替えて大人の余裕を見せつけるように涼しい顔を見せる。
「馬鹿言え。一度拾っちまったモンは最後まで責任持って育てるのがマナーって奴だ。それにあの娘1人を置き土産にしてみろ、鳳仙の旦那が黙っちゃいねぇ。お前さんは旦那とまた殺り合いたいかもしれないが、今度は上の連中にとやかく言われちまう。そん時ぁ、俺の腕一本じゃあどうにもならないさ」
本人が思っている以上に喋りすぎてしまったようで、阿伏兎は語り終わるとすぐさま前を向き直した。そしてため息を一つ。
上からの圧力や自分の身の危険を建前にしたものの、阿伏兎は自分の本心にも気付いていた。
「それに、兎は寂しいと死んじゃうんだよォ」
名前が荒く閉めた襖を阿伏兎はそっと開けて出て行った。
残された神威は阿伏兎の足音を聞きながらつまらなそうに呟いた。
「寂しいって、阿伏兎が?」