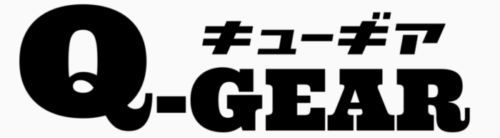口に出した後になって阿伏兎は自分が何を言ったのか、“誰“に”何“を言ったのかを自覚した。彼を含む団員の誰もが阿伏兎の死を想像した。
鳳仙の視線が阿伏兎に行く。視線だけで阿伏兎は瀕死だった。
「ほう、若造が口答えとは……」
「いや今のは、言葉の綾という奴で!」
なんとかして必死の言い訳を考えるが、焦って何一つ案が浮かぶ事はなかった。その代わり浮かんだのは、周囲の死体の山に混ざる自分の体だった。
──完全に終わった。道には迷い、仲間に茶化され、つい口を溢した呟きは聞かれてはいけない人物に聞かれてしまう。この惑星に着いてから何一ついい事はない。そうだ、この餓鬼とも会ったのは──。
そう思って鳳仙の手の中にいる少女を見ようとするが、そこに少女はいなかった。
「団長うしろッ!」
1人の団員が叫んだ。叫ばずとも鳳仙自身も気配を感じていたようで、言われる前に振り返り頭を守るように右腕を構えた。
いつの間にか鳳仙の手から脱走してた少女が、彼の右腕に齧り付いた。そのまま肉を引きちぎる勢いであったが、すぐさま鳳仙の左手によって弾き飛ばされる。
弾き飛ばされた少女は流れのまま阿伏兎がキャッチした。羽交い締めのようにされても、少女は再び鳳仙の元へと飛びかかろうと必死だった。口元が血に濡れ、先程までの無垢な少女ではなく、今はその姿から獣を彷彿させた。阿伏兎自身も、彼女を抑えている感覚よりも、狂犬を抑えているように錯覚させられた。
「その目、夜兎の本能か」
鳳仙は呟いた。引きちぎられそうになった右腕を見つめたが、少女の頭を掴んでいた左手の痛みに気付く。左手首に黒い小さな手形が付いていた。この少女がつけたものである事は明白だった。
「……興醒めだ。若造、その子供1人生かした所で何も意味はない。いずれは孤独で死に絶える。それでも其奴を生かしておくのか?」
鳳仙にどんな心境の変化があったのか、それは見ていた誰もが理解する事はなかった。鳳仙は死体の山、血の海を進んだ。たしかにこの少女を守っていたものはもう何も残ってはいない。彼の言う通りにこのまま生かしておいても、1人で生き延びる手段をこの少女が持ち合わせているようには見えない。
ならばどうすれば良いのか。そう考える暇もなく、両腕の中の少女の暴走を抑えるので精一杯だった。今はまだ子供であるが、これが大人であったら鳳仙との戦いに巻き込まれて阿伏兎ら団員は死んでいただろう。
「おいクソ餓鬼ィ!さっきまでの無邪気さはどこ行きやがった!……おーい誰か手伝ってくれ!」
まだまだ暴れる名前を抑え込む力を強めるが、一向に状況はよくならなかった。ついには助けを呼ぼうと周りの団員を呼び始めた。しかしその時、阿伏兎の足元に何かが落ちた。
ちりん、とどこから落ちたかわからない鈴が一つ。どこかで見たような気がするそれに、一瞬だけ腕の力が緩んでしまった。
──しまった!
そう思ったのだが、鈴の音を聞いて力が緩んだのは阿伏兎だけではなかった。
「……、ジジしんじゃったんだね」
阿伏兎の腕からこぼれ落ちるように倒れた名前は、地面に転がった鈴を拾い上げた。
鈴の既視感の答えは名前の髪飾りだった。彼女の髪にリボンと一緒に、2つ付いていた鈴の片方がなかった。
「みんなみんな、しんじゃったんだ。おかーさんとおなじだ」
ポツポツと阿伏兎のボサボサの髪に雨の滴が落ちてきた。ドラマの演出かと思わせるタイミングで雨が降って来た。団員はさっさと船へ戻ろうと撤収してしまう。阿伏兎もそこを離れようと名前とは逆方向に数歩進んだ。
雨音に混じって名前の嗚咽が聞こえてきた。その音に段々と阿伏兎の足取りがゆっくりになり、とうとう足が止まってしまう。
それでも名前は泣き止まない。誰もいなくなったこの町で、この少女はどうやって暮らしていくのか。そのまま飢え死にしてしまうのか?そんな事自分には関係ない。こんな数時間前に出会ったばかりの小娘の事なんか関係ない。そう思って阿伏兎は歩き出した。
「ったく、風邪引ィちまうぞ」
気が付くと阿伏兎は名前に自分の傘を差し出していた。自分は雨に濡れながら、名前が濡れないように彼女の頭上で傘を開いた。
「ぅぐ、おじさんのおうち、そっちじゃないよ」
阿伏兎の足元で蹲りながら名前が言った。
──本当によく喋る餓鬼だ。
「みんなおうちかえっちゃったよ。おじさんもはやくおうちにかえりなよ」
「迷子のウサギを家に送るのがウサギのおまわりさんの役目ってもんだろ」
その一言で名前は振り返った。目から溢れる涙が止まらない。雨も止む事を知らない。段々と強くなっていく水滴に阿伏兎は頭をかいた。
「拾っちまったモンは責任を持って育てるしかないさ」
仕方ない、そう言って阿伏兎は名前に手を差し伸べた。
「──阿伏兎ォォォ!!!!」
名前が阿伏兎に向かって必死に手を伸ばした。そんな彼女の姿を見た阿伏兎は鼻で笑いながらも、その手を掴もうと使える方の腕を掲げた。
「親と子って奴はいつのまにか立場が逆転するもんだ。お世話する方がいつのまにかされる方になる。手を差し伸べる方がいつのまにか、手を差し伸べてもらう方になっちまうなんてなァ」
名前に支えられながら阿伏兎は壁にもたれかかった。
「油断しすぎだよ」
名前は阿伏兎の腕と足の怪我を確認する。流石は夜兎族なので、このくらいの怪我であるならまだ平気だろうと彼女は判断した。どちらにせよこんな場所では応急処置程度のことしかできない。彼女は出血を止めるくらいしかしなかった。
その姿を見て阿伏兎はニヤリと笑った。
「しばらく口聞かないってヤツはどうした?」
ぁ、と名前が小さい声を漏らすがすぐに諦めた様に阿伏兎から顔を逸らした。
「……、反抗期はもうお終い!」
いじられたお礼に包帯をきつ〜く巻き上げると、今度は阿伏兎が小さく唸った。包帯を結び終えた名前は真っ直ぐ阿伏兎を見つめた。
「たとえ手足がもがれても、生きていればわたしが義手でも義足でも作るから。今度また危険なことがあっても絶対生きて帰ってきてね」
彼は一瞬驚いた顔をしたが、「ま、せいぜい頑張りますよォ」と鼻で笑った。
突然、吉原の真っ暗な空が唸り声を上げた。少しずつ開き始めていく天井を見上げた名前からはすぐさま驚嘆の声が漏れる。
「空、じゃなくて天井が……。あ、まずい!ダンチョーの傘預かってるんだった!!ダンチョー焼け死んじゃう!」
そういえば神威から傘を預かっていたことを思い出して慌てて傘を取り出す。真っ暗な空に一直線の光が差し込み始めた。2人がいる場所は物陰になっているが、神威がこの場所に向かうのに傘がなければ下手すれば死んでしまう。
「いっそ死んでおいてもらえ」
「そんな事言ってるとバチが当たるヨ」
「もう当たってるさ。2人のクソガキの子守なんて、とんだバチがな」
ため息混じりに呟く阿伏兎を見て名前は小さく笑う。そんなこと言っても、もう何年も一緒にいる。きっとこれからも一緒にいるんだ、そう思った名前は傘を持って立ち上がった。
「とりあえず安静にしててね。絶対だよ。終わったら迎えに行くから!」
「迎えに来なくていいさ。どうせ団長は俺に処分を下すはずさァ」
弱い奴に興味がない神威は、特に彼の妹に負けた自分を絶対に許さないだろうと阿伏兎が言う。そう言われた名前は少し悩んだが、そのまま立ち去ろうとする。
「ダイジョーブ!」
親指を立ててにっこり笑う名前に阿伏兎は嫌な予感しかしなかった。どこから来るのだお前のその自信は!とツッコミたかったがそれをグッと抑えた。しかしあの団長にこの娘が敵うわけがない。期待しないで待っていると伝えて去っていく彼女の後ろ姿を見守った。
いつも阿伏兎が彼女をおんぶする側であったのに、今日はその逆だった。落ちていく阿伏兎の腕を取った名前はそのまま彼を背負って、この物陰に運んだのだ。キチンと応急処置もして、上司に傘を届けると言って行ってしまった。
「ったく、いつのまにこんなに大きくなっちまったんだ?」
怪我をしている阿伏兎を置いて、名前は今来た道を引き返す様に建物の屋根を蹴った。神威の元に傘を届ける、というのは実は名目だった。彼女は決着をつけるつもりだった。
今まで目も合わせず、言葉も交わさず。もう前に進むことはないと諦めるのはもう止めよう。これが最期のチャンスだ、と。
「反抗期はお終い。本当に、お終いだよ」
まるで夜が明けるように強くなってくる日の光を自分の傘で受け止めながら、名前は父である鳳仙の元へと向かった。
全速力で神威の元へ向かった名前がその場にたどり着いた時、すでに銀時と鳳仙の戦いは決着が付いていた。
神威は建物の破片で完全に開かれた天井からの光を防いでいた。しかし傘を持った名前がこの場に到着するとすぐに手を出した。
「名前、傘」
ありがとうも何も言わずに名前から傘を受け取った神威は、楽しげに鳳仙が倒れる瓦屋根に飛び移った。そして彼に挑発する様に話しかける。その姿を名前は遠巻きから見守っていた。
すると1人の女性が支えられ、地面に這いつくばってでも鳳仙の元へ寄り添った。名前は一目で彼女が日輪であるとわかった。
光に呑まれ何も見えなくなった鳳仙を照らすように日輪は彼を笑顔で包んだ。鳳仙も安心した様に少しだけ笑った。まるで親子の微笑ましい日常の一コマを切り取ったような、今までの2人の関係からは信じられないその光景。それを見た名前は気付けば2人のそばまで来ていた。
「太陽を愛していた、ねぇ」
シワシワに枯れた老ぼれを見下す様に冷たい目で見つめる彼女に日輪は驚いた。
「その声、名前か」
鳳仙も失われていく視界の中央に彼女の姿を捉えた。彼が真っ直ぐ彼女を見つめるのは、彼女を殺し損ねたあの日以来だった。
「あれ、わたしの名前おぼえてたんだ。こりゃー本当にお日様の下で居眠りしたがってた普通のおじいちゃんだったのかな?」
日輪の言葉を素直に信じられなかった名前は屈んで煽る様に鳳仙の顔を覗き込んだ。
──太陽が好きな普通のおじいちゃん?
そのために一体何人が犠牲になった?自分の母親もコイツに殺されたのに、それが実は居眠りしたかっただけの普通のおじいちゃんだった、なんて名前は信じたくなかった。
しかし近付いた名前の顔を見た鳳仙は微笑んだ。
「やはり母親に似ている。……フッ、そうか。あの女も日輪と同じく……」
鳳仙は名前と日輪を交互に見た。
名前をその母親と重ね合わせ、太陽が2つ目の前に存在していると認識した。本当に欲しかったものは、2つとも近くにあったのに手放してしまった。だが、今ようやく再び手元に戻ったのだ。しかし、目の前に映る名前の笑顔を見て鳳仙は何かを察して、それを受け入れた。
名前が自分の元へやってきたのは、母や育ての親を殺して自分を捨てた、憎んで愛していた太陽の元で朽ちる無様な男にトドメを刺す為だと推測した。夜兎の「親殺し」の風習。かつて、三日三晩戦い続け決着がつかなかったあの男に、自分の弟子である神威がしたのと同じように……。その時を待って鳳仙はゆっくりと目を閉じた。
彼の期待に応えるように名前は右手を高くかざした。
「普通のおじいちゃんだって?残念だけど、もう遅いよ」
「やめっ……!」
日輪の叫び声にも全く動じず、名前は鳳仙に向けて手を振り下ろした。