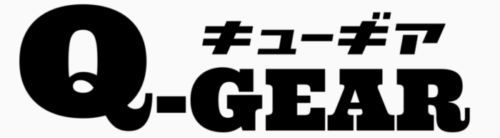太陽の真下。星海坊主は鳳仙の墓に軽口を浴びせた。夜兎の墓をこんな場所に作るなんて、そう鼻で笑う。
銀時が言うには、遊女たちの手によって作られた鳳仙の墓。せめてあの世ではいっぱい日の光を浴びて欲しいとの願いが形になったものだった。
墓標に彼の傘。星海坊主は見覚えのあるそれを見てフッと笑う。しかしその側に桜の小枝が突き刺さっているのを見た。それを引っこ抜いて空にかざした彼の後ろで銀時も目を見開いた。
「そりゃ桜じゃねェか。なんでこんな季節に……」
桜の時期はもうとっくに終わっている。しかしそれでもこの花は元気に花弁を風に靡かせていた。
「いや、これは地球の桜じゃない。確かどこかの惑星名物の一年中咲き続ける桜だ。えーっと、どこだったかな……」
星海坊主が「最近物忘れが激しい」と言いながら惑星の名前を思い出そうと毛が生えていない頭をかいた。
すると銀時の背後から聞き覚えのある声が響いた。如何にもバカっぽいマヌケな高い声。彼女は星海坊主がド忘れした惑星の名前を、彼の代わりに銀時に教えた。
惑星名を聞いた途端に星海坊主は「それだ!」と顔を上げて振り返った。そこには傘をさした名前の姿があった。彼女は続けてその桜の品種を告げる。
「お母さんの故郷の花だよ。お母さん、この花が好きだったみたい」
名前の言葉に銀時は納得がいく。鳳仙の最期に立ち会った彼女が、彼の腕に持たせた花はこの桜と同じだった。この花を持って母親と仲直りしろと言ったのはそういうことだったのか、と銀時は少し笑う。
「そしてわたしの名前の由来にもなってる」
当然のように自然に、流れるようにそっと銀時の背中にくっつくと名前はニッコリと笑う。
「どーりで、こんな一年中脳みそお花畑のポンコツ娘に育つ訳だ」
銀時は真顔で名前を引き剥がす作業に移った。しかし彼女は元々くっついていたかのように離れなかった。引き剥がそうとすればするほど、身体に回された腕の力が強くなる。
「名前。良い名前でしょ?」
名前は満開の笑みを浮かべながら銀時との攻防を続ける。彼女の姿に星海坊主は疑問を投げかけた。
「それはそうとして、この桜はほぼ絶滅したと聞いたが……」
星海坊主の言葉に銀時も名前も動きを止めた。
そもそも地球ではない惑星名物の桜の木が江戸に生えていることが星海坊主には信じられなかった。それに名前の母親の故郷はすでに滅んだはず、と彼は付け加えた。
その問いに名前は笑って答える。
「わたしも見かけた時びっくりしたよ。これ、あの場所に一本だけあったんだ」
「あの場所……、吉原にか?そういえば、一本だけ木が生えてたような、そうじゃないような」
銀時は朧げな記憶を辿るが、ぼんやりとしたまま答えは出なかった。今度日輪や月詠にでも確認してみるか、そう思いながら隙を付いて名前を身体から引き剥がす事に成功した。
「吉原に一本だけ、か。フッ、アイツもなんだかんだ妻への愛情は枯れてなかったようだな」
「ま、あなたの頭皮は枯れてるけどネ」
「今それ関係ないよねェ!!!」
星海坊主をからかいながら笑顔を浮かべる名前を銀時はじっと見つめた。
娘の名前の由来になった花を、妻が愛した故郷の花を吉原で密かに育てていた。鳳仙は日輪が言った通りの人物だったのだと思い知る。闘っている最中はそんな事考えもしなかった。いや、考える余裕なんてなかった。それほど鳳仙という男は強かったのだ。
しかし、それでも彼が人間と変わらない愛情を持っていた事に銀時は笑みが溢れた。
「名前。良い名前じゃねェか」
「あっ、初めてわたしの名前呼んでくれた!!」
銀時が彼女の名前を呼んだことで、名前は再び彼に抱きつく形になった。今回もギュッとくっ付いて、うんともすんとも言わない彼女。銀時は嫌がってはいるものの、引き剥がそうとはしなかった。
星海坊主は2人の姿を見守った。そして鳳仙の代わりに、元気な名前の姿を目に焼き付けた。彼は心の中で鳳仙に「馬鹿な事をしたな」と嘲笑う。しかし、自分も同じように神楽をほったらかしにして、宇宙中を飛び回っている事を思い出して苦笑した。
「……、元気でな」
誰に向けて言った言葉なのかはわからない。
星海坊主は帰り際に桜の枝を名前に渡して去って行った。
「でもよ、桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿っつー言葉があんだよ。レア物の桜の枝を切るなんて、そのまま桜が弱っちまったらどうするんだ?」
一年中花を咲かせる桜でも、枝を折られれば弱いようで、下手すれば枯れてしまう。せっかく江戸で生き延びたそれを殺してしまうのは勿体無いと銀時は訴えた。あの時と今回で、もう二度も名前によって枝を切られてしまっている桜。いくら死に際に供える為だとしても、やはり馬鹿な事をしやがってと彼は付け足す。だが、名前は首を振った。
「あの場所にはもう桜は必要ないよ。それでも、“おじいちゃん“が残した桜を残したいのなら、みんなでお世話すればいいと思うヨ。わたし的にはもうあの桜はお役目ゴメンだと思うケド」
「お前もお役目御免だろーが」
銀時が言った次の瞬間に名前の服のポケットが小刻みに震えた。原因は中に入っている通信器で、彼女はそれを取り出して通話ボタンを押した。用件は任務で別の惑星にいる阿伏兎からの帰還命令だった。すぐにも「えー!」と銀時と離れたくない彼女は抵抗したが、しばらくしたら銀時から飛び降りた。やる気のない返事をした後通信器を切ると、そろそろ限界だと傘をさした。流石にこんな炎天下の日当たりが良い場所で傘をささないでいるのは自殺行為だった。もう時期干からびるとこだったと冷や汗を拭う動作をする。
「干からびとけバカ娘」
「ざんねーん!まだまだピチピチの女の子だもーん!」
銀時からの冷たい視線もなんのその。彼に背を向けて傘で彼からの言葉と視線を跳ね除けた名前が、軽く呼吸を整えてから鳳仙の墓の前に立った。
「やっぱりあなたのこと、父親とか思ってないヨ。でも、わたしには阿伏兎がいるからね。だから今も昔も寂しくない」
名前が思い出すのは、あの日自分に傘をさして手を差し伸べてくれた阿伏兎の姿。そしていつも飛び乗っている大きな背中。
気付くのが遅かったとは言え、鳳仙も日輪によって救われていた。どんな人間でも宇宙人でも、手を差し伸べてくれる存在がいる。その手に気付く事ができるか、その手をしっかりと握る事が出来るか。
人生は重要な選択肢の連続だ。
「……あなたはあっちでお母さんと仲良くね。あとは殺しちゃった人たちにはちゃんと謝って回るんだよ。ごめんなさいってね」
罪が許されることはない。名前には鳳仙が天国に行ったとは思えなかった。彼はそれくらいの事をしたのだ。それでも贖罪のチャンスくらい与えてもらえるように、閻魔大王様に頼んでおくねと名前は笑う。
「きっとお母さんも一緒に頼み込んでくれるから、2人で一生懸命頼み込んでね。あとは……」
ほかに何か伝えたい事がある気がして名前は空を見上げてそれを思い出そうとした。しかし真っ青な空を、美しく光り輝く太陽を見ると何も浮かばなくなってしまった。
ギラギラと熱い視線を送る太陽。その光に照らされる傘。海の波は寄せては返すのをやめない。太陽は空があるから輝ける。波は大地があるから打ち寄せられる。誰にでも居場所がある。鳳仙の隣に居るべきなのは自分ではない。
名前はため息混じりに笑うと、しゃがみ込んで桜の枝を墓標の隣にそっと添えた。
「わたしはわたしの居場所に戻るよ。それじゃ、バイバイ」
名前は照れ隠しのように言い捨ててはすぐに歩いて行ってしまう。後ろにいた銀時にお別れのハグを要求するが、それはすぐに拒絶されてしまう。飼い主にじゃれつく犬のように、銀時の周りをうろうろしていた名前。すると海からの突風が彼女の背中を押すように吹いた。
──名前。
同時に背後から声をかけられた気がして、名前は立ち止まって振り向いた。
そこにあるのは崖の上にある墓と、桜の花だけだった。それでも名前は笑う。もしかすると、今そこに自分の父と母の姿を見たのかもしれない。いってらっしゃいと背中を押す2人を、いつまでも自分を見守ってくれる存在を認識したのかもしれない。彼女はそれに応えるように、2人に向かって大きく手を振った。
「いってきます!」
誰かが言った。
「地球は青かった」
お手製の船で宇宙から地球を見つめた名前も同じことを思った。段々と遠ざかる愛しの人、愛しの江戸。次に遊びに来れるのはいつなのか、なんて相変わらず呑気な事を考えているうちに第七師団の船に追いつく。名前が毎度船に激突する形で帰ってくるので、阿伏兎の命により作られた彼女専用の船着場に船を停めてはそこから飛び降りた。ふぁー、なんてあくびをひとつ。阿伏兎に呼ばれるまま帰ってきた彼女は、次の任務が何か一瞬だけ考えたがすぐに忘れる。地球の想い人は大好きだ。しかしそれ以上に大好きな彼の背中を見つけた名前は走った。
また団長に厄介ごとを押し付けられたのだろう。頭を抱えて猫背気味に歩くその姿。いつもの姿を見つけた名前は元気よくその背中に飛び乗った。
「ただいま、阿伏兎!!」