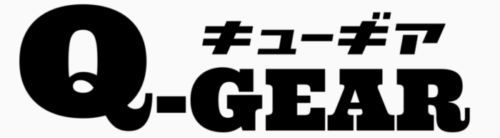名前が目覚めた時、そこにあったのは知らない天井だった。
場所は病院の一室のようで、医療器具が彼女の隣に並べられていた。手首にはチューブが繋がれて、顔には酸素マスク。器具の奥、窓の外では雨が降っているようで、窓ガラスが曇って結露が一滴窓枠に滴れた。
起き上がろうとした身体には激痛が走った。その痛みを抑えるように腹部に手を当てると、左手の薬指にここにあるべきものではない指輪がはめてある事に気づく。
「どうして、これはあの時銀時に……」
夫との約束を守るために、銀時に預けたはずの指輪がそこにはあった。いつの間に自分の手に戻ってきたのか、名前の記憶には残っていない。
自分はどうしてベッドの上で寝ているのか、確かそれは──。
微かだが、何かの感触を左手が覚えている。
「よっ。ようやく目が覚めたか」
「銀時…、あの人はどこに…?」
小さい花束を片手に持った銀時が名前の病室の扉を開いた。いつも通りの死んだ魚のような目を、真っ直ぐ名前に向けた。
目があった名前は、銀時に恐る恐る尋ねた。聞くのが怖かったのか、震える左手を押さえて一呼吸置いてから口を開いた。彼女の気を失う前の記憶が正しければ、あの人は……。
「お前の事頼むってさ」
目を逸らさずに銀時は言い放った。
その一言だけで何が起きたか、あの人がどこにいるのかが理解できてしまう。悔しさなのか悲しさなのかわからない感情が名前を襲う。その反射で左手を強く握り込む。
銀時はパイプ椅子を引き寄せて、ベッドのすぐ横に座った。何から話すべきか、頭をかきながら悩んでいる間に、数秒だけ静寂が病室を包んだ。
銀時の頭でまとまらなかった事をとりあえず口に出そうと息を吸い込んだ瞬間、名前の方が先に口を開いた。
「結局、私はあの人の事を救えなかったのね。攘夷戦争のあの時もそうだった。口だけで何一つあの人の助けになれなかった」
震えながらも吐き出されたその言葉たちに銀時は頭を抱えた。はぁ、と盛大なため息をついては気不味そうに名前を見た。
名前は左手の薬指を一心に見つめたまま震えていた。かつての勇敢な彼女を知っている銀時は、彼女の姿に違和感しか抱かなかった。
「人間変わるモンだな。薙刀ぶん回してた女が、今やひ弱な女に成り下がっちまったよ」
今の名前は皮肉を言われたところで感情が動くほど安定した精神を持っていなかった。反論もできずに震える姿は、雨の日に捨てられた子犬を見ているようで銀時にとっても良いものではなかった。
その後会話もなく、数分が経過した。彼女らしくない姿に苛立ったのか、雨のじとじとした空気に嫌気が差したのか。銀時が急に立ち上がった。
それまで俯いていた名前が驚いて顔を上げると、銀時が手を差し伸べていた。
「立てるか?」
「なんとか、歩けるかはわからない」
名前は銀時の手を取るつもりも、病室から出る気も一切なかった。しかし銀時の真っ直ぐな目を見てしまったその時にはもう、導かれるように彼の手に触れていた。そして気付いた時にはもう病室の外の廊下へ一歩を踏み出していた。
ハッとした時にようやく忘れていた痛みが彼女の身体を襲った。その様子を見た銀時は一瞬の判断で名前を自身の背中におぶって廊下を走り出した。
「坂田さァァァん!!その人重傷患者だから!!ついでにアンタも怪我してんでしょーが!」
「うっせー!!少し借りるだけだボケ!!」
勢いで走り出したが、その騒がしさに気付いたナースと医者が銀時を止めようと叫んだ。確かに名前は重傷で、本来ならある程度傷が治るまで安静にしていなければいけない状態だった。しかし銀時をよく見ると腕に包帯が巻きつけてあり、彼も万全な状態ではなかった。
名前が何がなんだかわからないまま銀時におぶられたまま、院内の一室へと連れ去られた。厳重な扉を開くと、薄暗く少し不気味な部屋に通された。
その一室の真ん中に、ポツリと真っ白なベッドが1つ置かれている。名前は自力で立つ事が出来ず、銀時に寄りかかるようにしながらベッドを見つめた。
ベッドは白い布で何かを覆っているが、布の重さでうっすらと人型が浮かび上がっている。
名前には一目で誰が眠っているのかがわかってしまった。自分なりに覚悟をしていたつもりであったが、目を閉じたままもう2度と起き上がる事がない彼の存在に目を背けた。
「救うとか救わなかった、救われただの俺にはよくわかんねぇけどよ。お前の旦那が幸せだったって事ならよくわかる」
「……どうしてそう言い切れるの」
震えた今にも途切れそうなか細い声で、なんとか言葉を紡いだ。名前が最後に“あの人”を見た時の事が脳裏でフラッシュバックする。
自分を庇ってあの人は亡くなった。名前の記憶は間違っていなかった。確かに名前を庇った事で、大男の一撃を受けて彼女の夫は亡くなった。
「幸せだったなんて、私のせいであの人は亡くなったの。幸せなはずがない!」
「じゃあ見てみろよ、アイツの最期を」
泣き叫ぶような名前の声が狭い部屋に響いた。それに間髪入れずに銀時も声を荒上げる。そしてそのまま、ベッドに横たわっている人物の顔を包んでいた布を剥ぎ取った。
怖くて見たくなかったあの人の死顔を見て名前は一瞬動けなくなった。まるで世界が止まったように、ピクリとも動かなかった。しかし彼の死顔の表情を理解できた時、名前の瞳に溢れた涙が一滴こぼれ落ちた。
「ッ…!」
「……ったく、幸せそうな面しやがって。人騒がせな野郎だ」
止めようとしても止まらない涙をなんとか抑えようと名前は必死に涙を拭うが、心の底から溢れた感情を止めることは出来なかった。なんとか彼にし損ねた別れの挨拶をしようと口を開こうとするが、口を開いて出るのは嗚咽だけ。ならばせめて、今度は彼の顔を目に焼き付けようと必死に見つめた。
男の死顔は泣いている子供をあやすような、そんな優しい笑顔だった。
「坂田さんそこは入っちゃダメだって!」
数分後看護師に見つかってしまった2人は長い説教を受けながら病室へと戻った。
「おはようございます。しばらくお休みを頂いてましたが、今日からまたビシバシ働きますのでよろしくお願いします!」
数日後、退院した名前が普段通りに真選組に顔を出した。女中仲間は精神・身体の状態を心配したが、名前はいつも以上に気合を入れて働く事で両方共快調である事をアピールした。
「名前ちゃん、少し時間あるかい?」
仕事も順調に進み、一休みしようと思っていた所で近藤に声をかけられた名前は局長室へと足を運んだ。
「えー、なんというか、苗字くんの事なんだが……」
局長室で2人向かい合って座るが、近藤の方は呼んでおいて何故か居心地が悪そうに言葉を詰まらせる。名前を呼んだのは、彼女の夫の事についてだった。
「まずは、すまなかった!!!」
「どうして近藤さんが謝るんですか!?」
覚悟を決めた近藤は勢いよく頭を畳につけて土下座の体勢になった。いきなりの事に驚いた名前は急いで近藤の側により、顔を上げるように言った。
「苗字くんの死は真選組の不手際が原因だ。親友である俺が彼を守れなかったんだ。本当にすまなかった」
「それは違います!!とにかく顔を上げてください!!」
これでもかと額を畳に擦り付ける近藤と、なんとかそれを引き剥がそうとする名前の攻防は、たまたま部屋を訪れた土方の声によって終止符を打たれた。
名前の夫と交友関係のあった近藤にとって、彼の死が自分の責任であると追い詰めていた。あの日自分が道に迷っていなければ、こんな事にはならなかった、と。
涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった顔のままの近藤を、土方がどうにかしてなだめている。納まりがつかないという事で、名前は仕事に戻るように土方が促した。
「あの人は近藤さんの事を恨んでなんかいませんよ。いつも家では近藤さんとのバカ騒ぎについて楽しく話してましたから。きっと、今もあっちでその話でもしているんだと思います」
そう言って名前は局長室を出た。その言葉は再び近藤の感情に火をつけたようで、わんわん泣き喚き始めた。呆れたように土方がため息をついた。しかし用を思い出して急いで局長室の扉を開けた。
「忘れ物だ」
「……!これは?」
部屋を出た名前に向かって土方が何かを投げた。名前はそれを受け取ると両手を開いてその正体を見つめた。
それは銀色に輝くペンダントだった。楕円形のシンプルなもので、分厚く頑丈そうなものだ。
「開ければわかる」
そう言って土方は部屋へ引っ込んでしまった。
「開ければ」という言葉に名前は疑問を抱いた。どうやらこのペンダントは内側に写真が入るロケットペンダントのようだ。言われた通りに開くと、そこには名前の写真が入っていた。いつ撮った写真だったか、もうすっかり忘れてしまったが、写真には笑顔の名前が写っていた。
写真とは反対に、名前は持ち主の顔を思い出して少し寂しそうに笑った。そして名前が付けるには少しだけ長いペンダントを首から下げてから、再びペンダントを手に取って見つめた。
「土方さんが渡すタイミング失って、ずっと持ってたんでさァ」
「わぁっ!びっくりした、沖田くんか」
余程集中してたのか、正面から歩いてきた沖田に気付かず肩を跳ね上げた名前。
「チッ。もう少し思い出すのが遅けりゃ、遺品窃盗として土方の野郎を牢屋にぶち込めたのに……」
「おい聞こえてんぞ!!」
沖田の声に、奥の部屋にいる土方がキレたように叫ぶ。そのいつも通りのやり取りを見て、なんだか安心した名前だったが、ある事を思い出した。
「沖田くん、あの人の指輪は……?」
「そーいや遺体を調べた時、指輪はしてなかったようですぜ」
「……そうですか」
彼の遺品であるペンダントは無事に名前の手元へ届いたのだが、死ぬ間際まで彼がしていたであろう指輪は発見されなかったようだった。
たしかに変だ、と沖田も頭の片隅で引っかかっていたようだが、すぐに忘れたように局長室へ向かった。
「おーいみんな!土方さんが近藤さんを泣かせてるー!!」
「おい総悟テメェ!いい加減にしやがれ!近藤さんアンタもいい加減泣き止んでくれ!!」
くすくすと笑いながら、やり取りに耳を傾けつつ名前は仕事に戻った。
途中で山崎から借りた無残にも折れた刀の存在を思い出して本人に謝りに行ったが、なぜか山崎からは逆に謝られた。どうやら名前の刀さばきに感服したようで、折れた刀の事は大丈夫だと言って去っていった。
こうして今日も真選組での仕事が終わった。
門を出た名前は久しぶりの仕事に少し疲れた様子を見せて伸びをした。しかしすぐ後に、よし!と言って気合を入れるように声を上げた。
外はもう夕暮れ時であり、家へと急ぐ子供たちが1度だけ名前を見たが、それもすぐに興味の対象から外れた。
名前は子供たちとは違い、家ではなくある場所へと向かおうとしていた。
──あの日、橋から落ちる彼の手を掴んだ時、確かにあの指輪は彼の薬指にあった。それが遺体を調べた時にはすでになくなっていたとすると、指輪はもしかしたら海の底に沈んでいる可能性がある。それを探すために名前はあの場所へと向かおうとしていた。
「もう日が暮れるってのにどこに行こうってんだ?」
「……銀時」
家とは逆方向に歩き始めた名前を銀髪パーマが引き留めた。愛用のスクーターに跨ったまま、よっと片手で挨拶した。
「探し物見つけに行くの。そうだ、そのスクーターで連れていってよ、万屋さん?」
「残念ながらその必要はないようだぜ?探し物はこれだろ」
「……!!」
意地悪そうにニヤリと笑った名前の目の前に、これまたニヤリと笑った銀時が自身の左手を見せつける。まるで芸能人の結婚報道写真のように、手の甲を向けて銀色の指輪を主張した。
形勢が逆転したようで、先ほどの意地悪な顔から驚愕の表情に変わった名前が、無意識に銀時の手をつかもうとする。しかしその手は空を切った。銀時が華麗に避けたのだ。
「どうしてそれを!……ま、まさか、窃盗!?」
先刻の土方と沖田のやり取りを思い出した名前が怪しむように銀時を見たが、すぐに銀時がツッコミを入れる。
「ちげーよ!どうしたらそうなるんだよ!」
「いくら生活が厳しいからって強盗は……」
「ちっげーっつってんだろ!!」
銀時が海に落ちた名前とその夫を救助したあと、意識が戻った彼に手をつかまれ、その際に名前の夫は銀時に自身の指輪を託したようだった。それで指輪は遺体から発見されなかったのだった。
それにしても銀時の指にはまっている物は、彼の指のサイズにぴったりだった。銀時を茶化しつつ、彼の指輪を見て感心した名前。
「それで、わざわざ真選組の前で待ち伏せしてたのはこれのため?」
「べ、別に待ち伏せしてた訳じゃねーし?っと、そうだかんざし。返しそびれてたからよ」
「かんざし?」
かんざしと言われても名前にはパッと思い浮かぶ物がなかった。しかし銀時が懐から差し出したかんざしを見た瞬間に過去の思い出が蘇った。
生き別れる直前まで名前が持っていたかんざし。髪を伸ばしたら付けると約束していたものだ。
「今見ると安っぽいね、そのかんざし」
「っせーな!銀さんが頑張って小遣い貯めて買ってやったんだぞ?それを安いだの値段しか見てねー守銭奴が!」
「はいはいごめんって。……はい、これでいいんでしょ?」
怒る銀時の手からかんざしを引ったくった名前は、手際良くかんざしを使って髪をまとめあげた。
その姿を見た銀時は心臓がドクリと跳ねた。その後はただぼんやりと名前を見つめた。
この姿を拝むのにどれほど遠回りしたのだろうか。ようやく果たされた約束は意外にもあっさりとしたもので、その呆気なさに銀時は動けずにいた。
「銀時?おーい?」
「……は!よ、よし、返すもんも返したし、さっさと帰るぞ、ほれっ!」
名前の声にようやく正気を取り戻した銀時がヘルメットを名前に投げ渡した。ほれ、と言われても名前はキョトンとした顔で首を傾けた。
「帰るって?」
「あんな広い屋敷に1人で寂しそうだーって神楽がうるせぇからよ。暗くなる前にさっさと帰るぞ」
そう言ってヘルメットをきちんと身につける銀時の姿を見て、名前は嬉しそうに小さくつぶやいた。
「……素直じゃないんだから」
名前も同じようにヘルメットをかぶった。
「あ?なんか言ったか?」
「なーんにも。さぁ帰ろうか、神楽ちゃんに美味しいご飯作ってあげないとね」
急かすように銀時が名前に向かって手を差し伸べた。その手を名前は見つめた。
恩師と出会った時に差し伸べられた手、名前が最後に掴んだ夫の手、あの時の温もりを忘れる事はないが、もうその手には触れることができない。
だけど名前の前に出されたこの手は握ることができる。もう何も失いたくない。ねえ、だからもう──
「この手を離さないで」