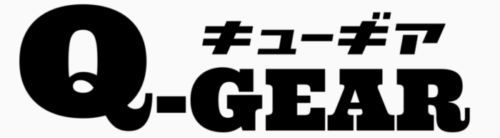太陽の光が差し込まない曇った街。雨か曇りか、2つしかない天気を繰り返すその街に一軒の花屋がある。廃墟ビルが密集する地帯にポツリと佇むその店は、女の店主が1人で切り盛りしているが、こんなところにまで来てわざわざ花を買いに来る物好きはいなかった。いつも一人で花の面倒を見ている、寂しい店だった。しかし陽が差さないというのに、店にある花は美しく咲いている。彼女が丹精込めて育てた成果だろう。
そんな物静かな店だが、今は店の外からわかる程に店内が荒らされていた。せっかく綺麗に咲き誇っていた花達は花瓶ごと、鉢ごと地面に倒され土がそこら中に転がっている。店主はその後始末に追われているようで、鉢や花瓶の破片を拾っては花を別の土に植え替え忙しい。
カランコロン、花屋のドアに付けられたベルが、物好きな客の来店を店主に知らせた。
「すみません。野蛮な連中のせいでこの街荒らされちゃって、今営業どころじゃないんですよねぇ。よっこいしょ」
店主は誰が来たかも確かめずに、ひたすら掃除を続ける。店で1番大きな鉢をなんとか持ち上げて元の場所へと運んだ。
店のほとんどの植物が外部からの襲撃により見るも無残な姿になっている。しかしそんな中でも、1束の花だけ無事で、その美しい姿を保っている。
「よかった、これだけは無事だ」
店主は胸を撫で下ろすと、その花を安全な場所へと移そうとするが、先ほどやってきた客がそれを止める。
「ちょうどよかった。いつもの買おうと思ってたところなんだ」
「……神威、帰ってたの」
客と店主は旧知の仲であった。店主──名前は納得した。こんな曇った街でわざわざ花を買いに来る奴なんてこいつしかいない。神威は数年経っても変わらない、相変わらずのニッコリ顔で花を指差すと名前に向かって硬貨を投げ渡す。
「見てたんだろ」
「見てない」
「嘘」
「そんな、宇宙一のバカが暴走した挙句に妹に負けるとこなんて見てたわけないでしょ〜」
「やっぱり見てたじゃないか」
硬貨を受け取った名前は手際良く花を包み、リボンで飾られた花束を作る。店で唯一無事だった花──神威が選んだ花──は、彼の母親が生前好んでいた花だった。神威は毎年母親の誕生日にこの花を花束にして渡していた。先代店主の名前の母親が丁寧に花を包んでいく姿を幼い彼女は直近で見ていた。あの時から変わらない花束を神威に手渡した。
「あ〜、今日命日だったのか〜」
「知ってた癖に」
「さぁ、覚えてないよ」
店にきて数分も経たないうちに神威は店を出た。毎年命日にはこうして花束を受け取りにやってくる。受け取った後は母親の墓に花束を置いて去って行く。いつもそうだった。
だから名前はその花を大事にしていた。神威の為。たとえ店を荒らしに来た者がいても、なんとしてもこの花だけは守りきろうと心に決めていた。その決意は揺らぐことはなく、なんとか先刻の街を荒らしに来た奴らから守り抜いた。だが、その為に多少の犠牲を払った事は彼女の身体がよくわかっている。
「……痛っ。傷口が開いたかぁ」
別の鉢を移動させていると左腕が痛んだ。服で隠れていたが、左肩から肘にかけて包帯が巻かれており、彼女の言った通り傷口が開いたようでうっすらと血が滲んでいる。
傷は痛むが、なんとか今日中に店内を元通りに戻そうと名前は作業を急ぐ。花瓶などの軽いものは全て移動できた。あとは重い鉢を全て動かすだけ。
しかし痛む左腕に思わず持っていた鉢を落としそうになる。
「しまっ──」
「俺も見てたよ。名前があの花を守ってたとこ」
ひょいと軽々鉢を片足で受け止めた神威がいた。そのまま鉢を蹴り上げ、蹴り上げられた鉢は神威の両手にすっぽりと収まる。
「この日になると俺が買いに来るからって必死だった」
「神威……、アンタ帰ったんじゃ」
「そうそう。帰ろうと思ったんだけど、帰り道に面白いものが転がってたから」
ほら、そう言って背後を確認せずに神威が店の外を指さした。そこには生物の山。この店を荒らしに来た奴らが、ゴミの山のように積まれていた。死んではいないようだが、重度の怪我を負っているようで、呻き声が名前の耳に届いた。
「ほ、ほぁ〜……」
流石夜兎族といったところで、神威の方は傷一つない。相変わらずの強さに呆気に取られた名前をよそに、神威は店内に落ちている適当な花を一輪掴み取ると、それを彼女に押し付けた。
「俺にも守らなきゃいけないモノがあったみたいだ」
「神威……。って、見てたんなら助けなさいよ!」
「あり?そんな事言ったっけ。覚えてないなぁ」
「嘘つけ!!」
逃げるように出て行く神威を追いかけるが、彼は建物の屋上へ登って一度もこちらを振り返る事なく、そのまま去っていってしまった。
その背中が見えなくなるまで見送った名前は、押し付けられた花に目をやる。薄ピンクの可愛いらしいその花。
「ネリネか。あいつ知っててこれを私に?」
顔を上げて周囲を見渡すが、もうその姿を確認することは出来ない。
「……そんな訳ないか」
ふっ、ため息にも似た笑いが唇から溢れた。店内に戻ると、そこはまだ荒れたまま。ネリネを空いている花瓶に生けると、再び作業に戻った。まだまだ店の掃除は終わりそうにない。
その様子を見守るようにネリネの花は名前を見つめた。
ネリネの花言葉──また会う日を楽しみに。